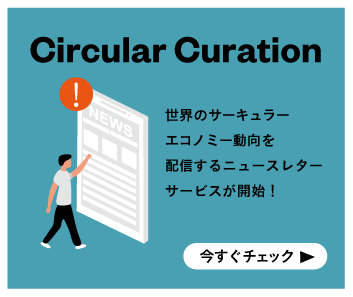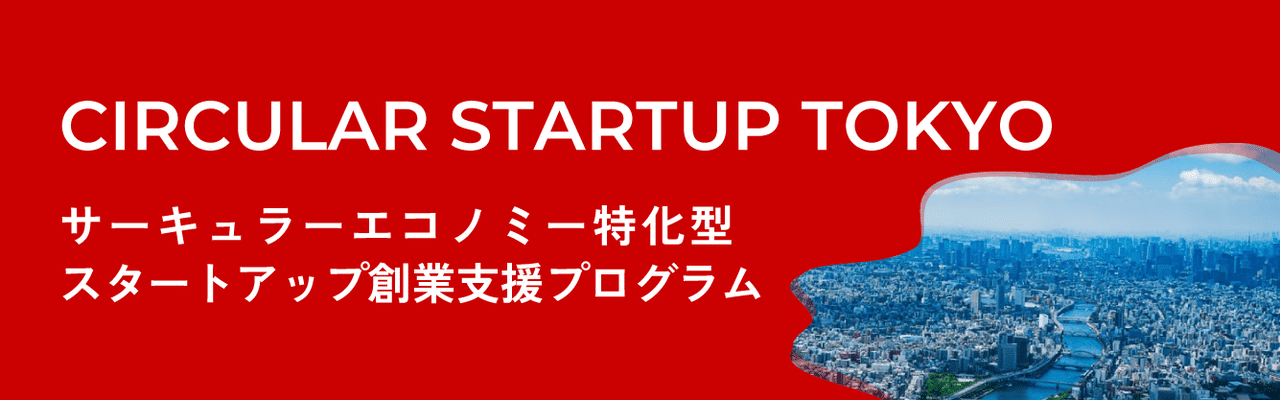Circular Economy Hubが定期的に実施している、サーキュラーエコノミー分野のフロントランナーの現場を訪れるフィールドワークをレポートする。
2023年7月の今回は、「公共コンポスト・循環型農園を通じたコミュニティづくり」をテーマに、東京都三鷹市にある鴨志田農園の鴨志田純氏から、公共コンポストと循環型農園の仕組みについて学んだ。
鴨志田氏は、コンポストを中心として消費者と農家がつながる「公共コンポスト」という循環の仕組みを構築し、自ら実践。また、コンポストアドバイザーとして日本各地で公共コンポストの設置と人材育成を行うほか、ネパールで生ごみ堆肥化の国家プロジェクトも推進している。
この日は、全国各地から集まった参加者19名で農園を訪問。まず一行は、鴨志田農園の野菜の販売も行う、量り売りとまちの台所「野の」を訪れた。「野の」は、豆類やスパイスや乾物、お酒などを顧客が必要な分量だけ販売、プラスチックや使い捨ての容器を使用せず利用できる量り売り店。店舗を経営する合同会社野のは、参加メンバー全員が出資し、出資額に関わらず平等に経営に参画、労働に携わるという特徴がある。地域とのつながりを重要視し、食の地産地消を目指す。


「野の」での昼食後、住宅街を抜け鴨志田農園へ移動。前半は、完熟堆肥づくりの基礎知識や公共コンポストの仕組み、堆肥を中心としたコミュニティデザインについて鴨志田氏より講義を受けた。講義では、鴨志田氏が取り組んできた、日本国内での公共コンポストの仕組みづくり、およびネパールでの生ごみ堆肥化の国家プロジェクトついても話を伺った。
社会課題解決のツールとしてのコンポストとは?
堆肥とは、主に(水、二酸化炭素、粘土鉱物なども使用)有機物を微生物の働きによって高温で発酵・分解・熟成させた肥料のことを指す。単に「肥料」と呼ばれるものは、土や作物に対して化学的な養分変化を与えるものを指すため、性質が異なる。
コンポスト(堆肥化)とは、微生物の力で生ゴミや落ち葉などの有機物を分解・発酵させ、有機肥料をつくることを指す。家庭から出る可燃ごみの約3割を占めると言われる生ごみは、その8-9割が水分で、焼却時には多大なエネルギーが必要とされる。コンポストは、生ごみ等の食品廃棄物を資源として活用するための有効なツールとして評価されている。
公共コンポストとは、コンポストを堆肥をつくるという役割のみでなく、さまざまな社会課題を解決するための公共インフラとして活用する考え方である。地域コミュニティを構成する単位である流域単位での資源循環や資源の再生産を考えるなど、ごみ処理問題と他の社会課題とを組み合わせて考えるという発想で、その地域が抱える課題を解決していくツールとなる。
生産者と消費者の対等な関係を構築する、地域支援型農業
鴨志田農園で導入している、消費者が農家に代金を前払いし、定期的に農作物を受け取るCSA(Community Supported Agriculture、地域支援型農業)についても学んだ。
消費者からの購入申し込み、代金前払いの制度があることにより、農家は販売計画を立ててから、それに基づく栽培計画を立てることができる。農家は、この仕組みに賛同してくれた消費者に定期的に野菜を届け、その野菜を使って出る生ごみを消費者が自宅で一次処理したものを、農園で二次処理をして完熟堆肥に。この堆肥を使って再び野菜を栽培し販売するという地域循環を生み出している。生産者と消費者間でリスクを共有し、対等な関係を構築しながら、農作物を食卓に届けるFarm to Tableのみならず、コンポストとして食卓から農地に還すTable to Farmも成立している。これは、サーキュラーエコノミーのうちの生態学的循環と極めて親和性が高いといえるだろう。
日本の農家の中で、年商500万円以上の収益を上げているのは全体の2割以下といわれる現状において、鴨志田農園は年商700万円、農家平均の2.5倍の売上をあげており、経済性とも両立できている。
コンポストが持つ3つの将来性
鴨志田氏は、コンポストが持つ将来性について、次の3つの軸を挙げる。
- 防災機能性:災害などによる断水時に、コンポストは排泄物を分解処理できるため、トイレとして使用できる。
- イノベーションの触媒:コンポストを軸に異なる専門分野の人と話をすることで、イノベーションが起こりやすくなる。たとえば、堆肥は農業資材の側面が強いがコンポストは公共性との相性が良く、防災トイレ以外にもコンポストからの熱源を利用した暖房機能など、新たな価値を創造できる。公共インフラとしての発展である。
- コンポスト葬:予想されている南海トラフ地震のような大規模な災害発生時、火葬場が機能しない状況が想定される。人間を堆肥化するコンポスト葬はそのようなケースへの備えになるのではないだろうか。
住宅街にある農園で、年間40種類の野菜を栽培
後半は、2800平米の面積で、年間約40種類もの野菜を栽培する有機農園の様子や堆肥作りの現場を見学。

集められた生ごみが時間をかけて堆肥になる場所「堆肥舎」には、近隣地域から集められた生ごみと基材が混ぜられ、半年間で半分ほどの容積になる。収穫した野菜でどのような料理を作るか、という最終形によって、野菜を栽培する際に使用する堆肥、ひいては適切な生ごみの種類が異なるという。

ちょうど収穫時期を迎えていたトマト畑では、鴨志田氏がその場で収穫したトマトを見学者に配ってくれた。その場で頂く獲れたては、味が濃く甘みがあり、みずみずしさも絶品である。
講義の中で鴨志田氏は、循環やコンポストなどに対して興味関心を持っていない人に、興味関心を持ってもらうこと、そのためには言葉ではなくデザインで伝えていくことの重要性を強調した。収穫された野菜の美味しさからその野菜に興味を持ってもらい、選んでもらうことで結果として環境負荷を下げることにつながるのである。
【関連記事】堆肥作りは、料理作り。公共コンポストで地域を“発酵”させるサーキュラーエコノミー
【関連記事】フェスで生ごみをコンポスト~京都音楽博覧会2022でのサーキュラーエコノミー的取り組み
【関連記事】京都から出るロス食材をシュトレンに。「八方良菓」に学ぶ、地域をつなぐサーキュラーデザイン
【関連動画】【アーカイブ動画購入可能】「サーキュラーエコノミーとコミュニティ」オンライン学習プログラム Circular X