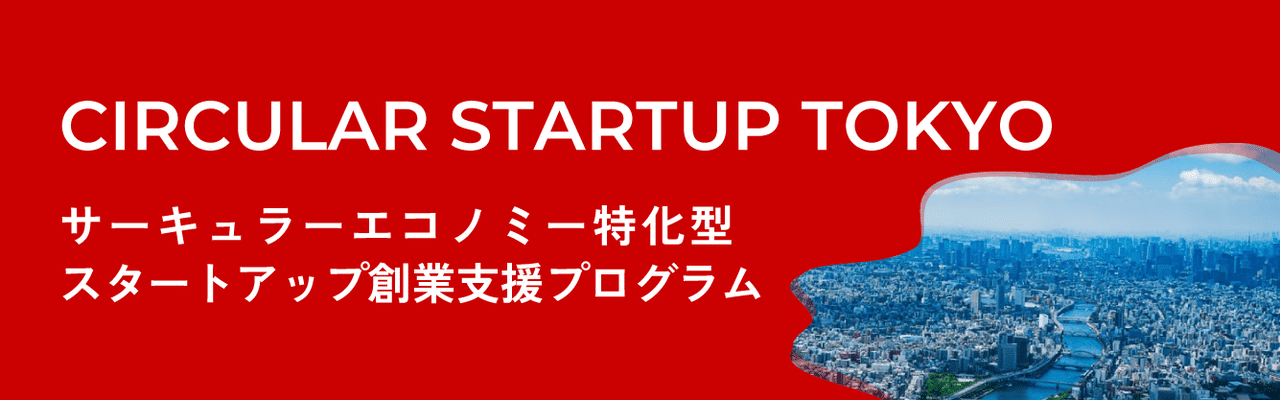どこかあたたかい茜色、ちらりと光る柳色、当たる光をやわらかく跳ね返す鼠色……。目の前に並ぶいくつもの色を見ていると、不思議と落ち着く。

これらの色は、どれも日本のどこかで生まれ、その土地と共に生きてきた物語を持つ。それはときに、空き家の解体で行き場を無くした屋根の瓦だったり、製作過程で欠けてしまった焼き物の破片だったり、もとあった場所から転がり落ちてしまった土の塊だったりする。
こうした土地固有の素材を塗料にすることで色として表出させ、地域の新たな物語を紡いでいこうとするのが、「NULL(ナル)」だ。2021年に千葉県いすみ市で実験的なプロジェクトとして始まり、これまで日本各地に眠るさまざまな素材から塗料を作り、それを通してものづくりのあり方を問いかけてきたNULL。今、塗料を起点に地域やその土地ならではの価値が活かされるエコシステム作りに向けて、大きく発展しようとしている。
今回は、NULLのクリエイティブディレクター・髙橋慶成氏に、ものづくりのあり方をデザインするNULLの哲学や今後の可能性について、話を聞いた。

多摩美術大学デザイン科グラフィックデザイン専攻卒、Camberwell College of Arts MA Illustration卒。ブランドの概念からVI、建築設計まで一気通貫でデザインするYTRO DESIGN INSTITUTEを経営。本業での経験値を活かしながら、ものづくりのあり方をデザインするプロジェクトとしてNULLを立ち上げ。
【NULL】Instagram
日本独特の美意識がつまった古民家の活用から、地域産の塗料づくりへ
学生時代は日本でグラフィックデザイン、イギリスでイラストレーションを専門に学んだ髙橋氏。学生時代の海外生活では、日本で生まれ育った者としてのアイデンティティを常に問われてきた。そうした経験が、民俗学や文化人類学、そして「日本独特の美意識」といったものに関心を持つ土壌を作った。
帰国後はブランディングを手がけるデザイン事務所を経営。スポーツチームや日本酒造のブランディングなどを手がけるなか、古民家の価値も探求するようになる。
「会社で建築設計を手掛けることもあるため空き家活用には関心がありましたし、地域の中で空き家をどう活かしていけるのだろうか、という問いが常に自分の中にあったんですよね。そんななか、僕も拠点としている千葉県のいすみ市で、創造系不動産という会社がやっていた空き家ツアーに参加しました」
地域における空き家活用の観点は面白い。そう感じた髙橋氏は、いすみ市で国土交通省が行う「空き家担い手事業」に応募し、採択されたことをきっかけに本格的に空き家活用に踏み込んでいく。これが、NULLを始めるきっかけとなった。
「いろいろと検討するなかで、空き家そのものではなく、まずは空き家に残っているものを活かして地域を盛り上げていこう、といった流れができてきました。そこで、 古材や古道具のリメイクを始めたんです。その過程で、NULLを手伝っていただいている特殊塗装職人の中村修平氏に出会い、 塗料の文脈で何かできないだろうか?という話が膨らんでいきました。 そうして生まれたのが、地域のさまざまな素材を粉砕して塗料にしてみよう、というアイデアでした」

髙橋 慶成氏
色合いもテクスチャーも。ひとつとして同じものはない、オリジナルな塗料
地域の古民家から回収した瓦。空き家の敷地内に地層から転がり落ちた土。海風で飛ばされてきた、海岸の砂。NULLの塗料の原料となるのは、地域で価値が見出されていない、廃材や未利用資源、天然素材などだ。髙橋氏によれば、工夫次第でほとんどの素材は塗料化できるのだという。

塗料の素材にした、千葉県・いすみ市の古民家から回収した瓦。
なかでも、日本全国に眠る未利用資源のひとつが、陶器の廃材だ。
「手仕事で陶器を作っている窯では、作品の完成度を非常に大切にするため、どうしても一定量の廃材が出てしまいます。そうすると、少しでも歪んでいたり傷がついていたりするものは行き場がなくなってしまい、現状その処分費用もかかっている状態です」
こうした素材を粉砕し、アマニ油やマツヤニといった天然素材を加えて作るNULLの塗料は、わびさびのある渋い色合い、そして個性的なテクスチャーが特徴だ。実際にさまざまな素材から作られたNULL塗料が塗られたタイルを触ってみると、スルスルと指が滑るもの、ザラザラと素材感が残るものなど、ひとつとして同じものはなかった。
塗った時の気候条件や日光の当たり方などで後々色が変わることもあるというが、それもまた人の手で操作しきれない時の移ろいを感じさせる、味わいのひとつだろう。
「NULLの塗料は、時間が経ってから塗り直すこともできます。金継ぎのように、違う色で塗り直しても面白いかもしれません。そうしていくことで、塗ったものに愛着も生まれると思うのです」

NULLの塗料で塗った、植物用のプラスチック製ポット。遠くから見ると陶器のように見え、柔らかかった素材も硬くなる。植物を取り扱い、ギャラリーでもあるGreen Thanks Supplyと共に行ったプロジェクト。

「塗る」という行為を、人とものづくりの関係性をつくり直す入り口に
価値のついていなかったものの使い道を見出し、活用していく。この部分だけを見ると、廃棄物を減らすことを目的としたシンプルな循環型ビジネスに見えるかもしれない。しかし、NULLの根幹となる哲学は、むしろそのプロセスにおいて、「人とものづくりとの関係性をデザインすること」にある。そのために欠かせないのが、関わる人を巻き込んで行うワークショップだ。
「新しいプロジェクトを始めるときは、最初に必ずワークショップをして、関わるステークホルダー全員に参加してもらうことを大事にしています。素材を粉砕するところから一緒に塗料を作り、作った塗料を椅子や壁などいろいろなものに塗ってみる。そうすると、みんな仕事やそれぞれの専門性を一旦忘れて参加してくれて、場がひとつになるんです。それがすごく大事だな、と」

瀬戸でのワークショップの様子
髙橋氏がNULLを通して、人とものづくりの関係性をデザインしようとする理由。それは、これまで髙橋氏がデザイン領域で仕事をする中で、現代社会において「ものづくりのあり方」に課題を感じてきたからだという。
「日本で育つと、自分でものづくりができるという感覚を得にくいと思うんですよね。現代社会では、どのようにものが作られているかを知る機会が限られているからです。そんななかで、『塗る』という行為はほとんどの人が簡単にできます。それを通して、『ものづくりって、自分でもできるんだ』と感じてもらいたいんです」

瀬戸でのワークショップの様子
「これはNULLのコンセプトでもあるのですが、環境問題の改善を進める上で、皆がものづくりを自分ごと化していかないと社会はなかなか変わっていかないと思っていて。どんなにいいプロダクトがあっても、結局はそのものと人との『良い関係性』が作れないと意味がない。サーキュラーエコノミーにおいてまず大事なことは、既にあるものの寿命をいかに伸ばしていくかだと僕は考えています。
人は自分が作ったものは簡単に捨てられないだろうし、大事にしようと思うはずです。だから、塗るという行為を通して、ものづくりに関心を持ってもらう。そうすることで、ものへの見方や関係性が変わっていくきっかけになるのではないでしょうか」

微妙な凹凸のある表面が光を当てると独特な表情を見せるアートピース。土台となっているアクリル版が透ける部分がきらりと光る。

NULLの塗料で作成したアートピースを飾った、人と自然が共生する社会の実現を目指すライフスタイルブランド・SANUの宿泊キャビンの室内。 ⒸSANU photo by Masaaki Inoue
塗料を起点に作る、地域のプレイヤーが主役のエコシステム
NULLを通して地域に眠る素材を活かしながら人とものづくりの関係を塗り直し、そこにしかない色で彩られた個性のある場所が日本中に増えていく。さらには、その過程のなかで地域のプレイヤーの活躍の場を作り、土地に根ざした経済的価値を生み出す新しいエコシステムを作っていく。これが、今髙橋氏がNULLを通して挑戦しようとしていることだという。
「廃材や未利用資源を塗料化して終わるのではなく、それを活用する一連の流れを、その地域や関わるステークホルダーにとっての経済的インパクトを生み出すものにしたいと考えています。だからこそ、そこで主役になるのはあくまで地域の人やその土地に根ざした企業といった、地域のプレイヤーであるべきだと思っています。
地域に眠る素材を地域の中で塗料化し、地域の人たちが自分たちで何かを表現する。そうしてみんなで作ったものを使ったり販売したりと、そこに暮らす人たちが価値として共有できる。NULLの役目は、その仕組みを作り上げることにあると考えているんです」

NULLの塗料で塗ったダルマのオブジェクト。
「もちろん、作家やアーティストの作品には大きな意味があるし、大事だと思っています。一方で、小鹿田焼(おんたやき)(※)に代表されるような民藝的なもの、人の生活の中で自然に生まれてくるものづくりが、僕は好きなんですよね。名もなきものだけれど、佇まいが綺麗で、使いたくなる。そういうものが、日本の地域でもっと生まれていったらいいなという想いがあって。
それこそ焼き物は地域ごとの特徴が表われているものづくり文化だと思うのですが、そういったものの廃材や天然素材を塗料化することで各地域の色が顕在化し、アーカイブができていく。個性のあるものづくりが、増えていく。そんな未来を、NULLで創っていけたらと思っています」
※ 小鹿田焼:大分県日田市・小鹿田の里で伝わる約300年の伝統をもつ民藝の器。日常での使いやすさと美しさを兼ね備えた「日用の美」を追求し、「世界一美しい民窯」とも言われる。
編集後記
取材を終えた後、自分とものづくりとの関係について、改めて考えてみた。
子どもの頃は、幼稚園の庭で泥に水を加えて毎日のように“チョコレート”を作っていたし、家でだって、紙を切ったり貼ったりして何かを作ることは、当たり前の日常だった。
それがいつからだろうか。ものづくりに関われる人は、一部の特別な人たちだけ。そんな風に思うようになっていったのは。そうなると、自分とものとの間には、「完成したものを手に入れて消費する」という無機質な関係性しか生まれない。これが、私たちがものを際限なく作り、簡単に捨てていく文化の根源なのだろう。そうした文化は、社会も自分の心も、どこか無機質なものにしていく。
一方で、ものを作ろうとしたときに生まれるのは、「もっとこうしたい」「どうしたら良くなるだろう」「ここを変えたら、もっと美しくなるかもしれない」「完成したら、あの人に見せたいな」……そんな、ぬくもりのある感情ではないだろうか。髙橋氏が取材中何度も口にしていた「愛着」とは、そうした感情の積み重なりのことを言うのかもしれない。
そして、そんな愛着のこもったものたちが溢れる地域社会で生きられたら──そこにあるのが、本当の意味での豊かさなのかもしれないと、感じるのだ。
【参照サイト】NULL(Instagram)
※本記事は、ハーチ株式会社が運営する「IDEAS FOR GOOD」からの転載記事となります。