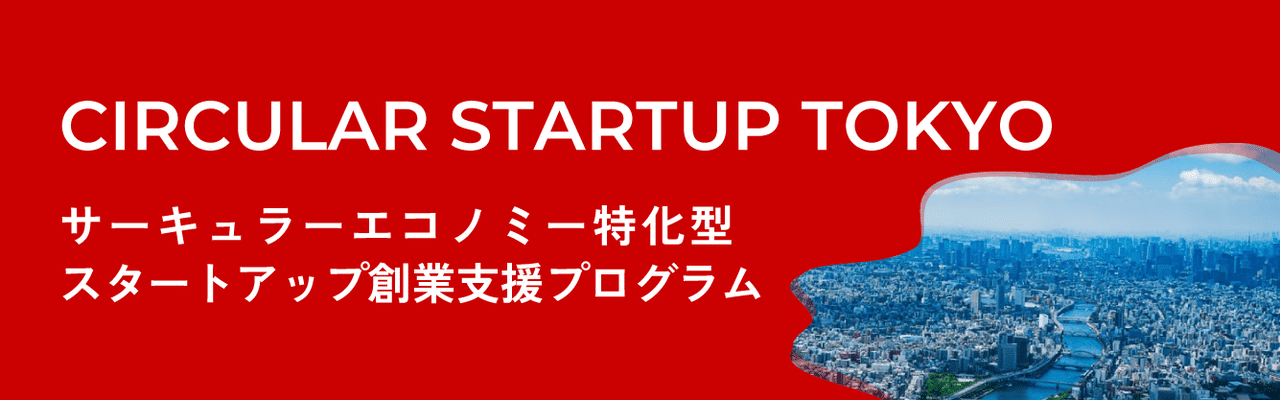「自然は直線を嫌う。」18世紀のイギリスの造園家、ウィリアム・ケントが残した言葉だ。
今、世界では「資源を採掘し、ものを作り、使って捨てる」という一方通行のリニアエコノミー(直線経済)から、廃棄や汚染を出すことなく資源を循環させ続けるサーキュラーエコノミー(循環経済)への移行が叫ばれている。
ウィリアム・ケントの言葉に沿って考えるなら、直線経済から循環経済への移行は、自然に嫌われるシステムから自然に好かれるシステムへの移行とも言えるかもしれない。
しかし、自然は本当に「直線」が嫌いなのだろうか?ドイツの数学者、カール・フリードリヒ・ガウスは、1801年に65,537本の「直線」からなる正65,537角形が定規とコンパスで作図可能であることを証明した。これが、「円」である。直線と曲線を区別するかどうかは、人間の眼差しの問題だ。
また、「自然は直線を嫌う」という言葉の裏には、人間が外部から自然を客体として観察しようとする眼差しがある。しかし、人間も動物の一種であり、自然の一部と考えるなら、人間が作った直線も自然の産物と考えることもできるだろう。
私たちはつい自然と人工物を分けて考えてしまいがちだが、人間が手を加えて創り出したものを人工物、そうでないものを自然だとするなら、もはや人類の活動が気候危機や生物多様性の喪失など生態系全体に多大な影響を及ぼしている現状において、人間が関わっていない手つかずの自然が地球上に存在すると言えるのだろうか。すべてが相互に影響を及ぼしあうシステムの中でつながっていると考えると、見えていたはずの境界線がとたんにぼやけ始めるのだ。
「循環」という概念は、こうした私たちが区別しがちな様々な概念の間に横たわる見えないつながりに気づき、両者を決して分けることができないものとして捉えることに長けている。このように考えていくと、循環するシステムへの移行とは、私たち人間が持つ眼差しを変え、今すでにあるこの世界を違った視点から捉え直すことなのかもしれない。
そもそもシステムとは人間の思考から立ち現れるものであることを考えると、何か大きなものを変えようとするよりも、一人一人が自分の中にいつの間にか身につけてしまった眼差しの偏りに気づき、物事に対する捉え方を変えていくことのほうが、循環する経済や社会への近道となる可能性もある。
目の前にあるものが廃棄物なのか資源なのか。「脱」を枕詞につけられたプラスチックや炭素は、本当に悪者なのか?循環する経済や社会というビジョンは、私たちにこうした本質的な問いを投げかける。本記事では、ウェルビーイング特集における「脱炭素」「再生」「多様性」「格差」「あたらしい経済」という他のテーマとのつながりの中で、「循環」という概念の本質を考えていく。
炭素は悪者?炭素の循環を考える。
2020年10月に菅首相が2050年までの「脱炭素」を宣言して以降、日本でも「脱炭素」という言葉が毎日のようにメディアを賑わせている。「脱」という言葉がつくと、何だか炭素が悪者のようにも聞こえるが、決してそうではない。
炭素は、言うまでもなくあらゆる生命の循環をつなぐ大事な元素だ。植物は大気中のCO2と水を使って光合成し、炭水化物を作る。人間も含めた動物は、その炭水化物を食べることで命をつなぎ、呼吸をしたり、死後には微生物によって分解されたり燃やされたりして、自らの炭素を大気中に戻していく。炭素は生産者である植物、消費者である動物、そして分解者である微生物たちの間を絶え間なく循環し、全ての生物が共生しながら繫栄するメカニズムを作っているのだ。
サーキュラーエコノミーの原点となる「Cradle to Cradle(ゆりかごからゆりかごへ)」という概念を提唱したウィリアム・マクダナー氏は、2016年に「Carbon is not the enemy(炭素は敵ではない)」という論文を発表し、問題なのは炭素そのものではなく、炭素が「in the wrong place, at the wrong dose and for the wrong duration(間違った場所に、間違った量、間違った期間)」置かれていることだと指摘した。

生物の死骸が堆積し、数億年以上の時間をかけて作られた地下資源の石油を地上に掘り起こし、燃焼させてその炭素を地上に放出すれば、炭素の循環が乱れてしまうことは自明だ。その意味で、今私たちがすべきことは、人間の活動をもとから地球上に存在する炭素の循環のリズムに合わせていくことだろう。
消費財大手のユニリーバは、「カーボン・レインボー」という独自の戦略に基づいて炭素の循環経済の実現を目指しているが、まさに問われているのは炭素の「循環」であり、その循環のリズムにどのように自社の事業を整合させるかだ。
Geosphere(地圏)から採掘し、Atmosphere(大気圏)に放出してしまった炭素は、植林による森林再生やDAC(直接空気回収)などのCO2回収・貯留技術を通じて再びBiosphere(生物圏)かGeosphere(地圏)に戻していくか、プラスチックなどの製品にし、外部流出をしないようにTechnosphere(人工圏)に固定する。そして、人間が活動に使用する炭素はGeosphereからではなくTechnosphereからの再利用か再生可能なBiosphereからの採取に限定し、それらを循環の収支を乱さないペースとリズムで利用していく。このように炭素の循環を正しくデザインすることが求められている。
再生とは、循環の原則である。
英国のサーキュラーエコノミー推進機関、エレン・マッカーサー財団は、サーキュラーエコノミーの3原則の一つに「Regenerate Natural Systems(自然のシステムを再生する)」を挙げている。
同財団が掲げる有名なサーキュラーエコノミー概念図「バタフライ・ダイアグラム」の原点でもあり、循環を「Biological(生物サイクル)」と「Technical(技術サイクル)」に分けて考えるCradle to Cradleの概念も、「Less bad(負の影響を減らす)」ではなく「More good(正の影響を生み出す)」を実現する「Regenerative Design(再生するデザイン)」を標榜している。
「再生」とは、一度働かなくなった状態を、再び働く状態に戻すことを指す。つまり、「自然のシステムを再生する」とは、自然に本来備わっていた循環のシステムをもう一度もとの状態に戻すということだ。そのためには、人間が自然のシステムを乱したり壊したりするスピードを緩めるだけの「Less bad」の考え方では難しい。人間の活動を通じて自然のシステムを整え、よりよくしていく「More good」に移行していく必要があるのだ。

これは、言い換えると人間という存在を自然が持つ循環のリズムの中にもう一度戻していく営みとも考えられる。人間と自然とを切り離し、外側から自然というシステムに働きかけるのではなく、人間を自然の一部として捉え、内側からシステム全体に働きかけていく。人間を自然が持つ循環という鎖の輪に再びつなぎ直す(リカップリングする)ことで、自らを再生のプロセスに組み入れるのだ。
日本各地の里山で「リジェネラティブ・バイイング」に取り組むラッシュ・ジャパンの細野隆氏は、リジェネレーションは性善説だと語っていた。里山は、人間が自然に介入し、関わることで豊かな生態系が保たれている場所だ。奥山でもなく人里でもない里山という曖昧な「間」に、人と自然とが共生しながら持続可能に繁栄する仕組みが作られているのだ。
2015年にCapital InstituteのJohn Fullerton氏が発表した「Regenerative Capitalism(リジェネラティブ資本主義)」の8原則の一つに、“Edge Effect Abundance”というものがある。これは、たとえば海と陸の間にあるサンゴ礁など、異なる生態環境の交わる境界線の部分に、異なる多様な生物が交わりあうことによって独自の豊かな生態系が育まれるという意味だ。里山も、まさにその事例の一つと言えるだろう。どちらとも言えない「間」にこそ、創造とイノベーションの余地があり、この「間」を捉えるのが、循環だ。
人間は自然を壊すのではなく、再生できるという考え方は、人間にも優しい。”Less bad” の思想を突き詰めると、自然にとって人間はいないほうがよいという結論になってしまうが、”More good”は、人間という存在を肯定してくれる。だから性善説なのだ。
直線経済を否定するのではなく、直線経済が残してくれたテクノロジーをはじめとする正のレガシーを活かしながら、循環経済へと移行していく。人間の存在を否定するのではなく、むしろ肯定的に捉えながら、自然と再生的な関係を作りあげていく。循環は、相手を否定するのではなく包むこみながら、よりよいシステムへと進化していける概念だ。
多様性は、循環を生む。
自然界のシステムを経済や社会といったあらゆる人間活動のお手本とするのであれば、「多様性」が重要なキーワードとなることは間違いない。自然界の循環するシステムを成立させているのは、まぎれもなく「生物多様性」だ。
生物多様性は「遺伝子の多様性」「種の多様性」「生態系の多様性」からなり、あらゆる生物は相互に影響を及ぼしながら生きている。私たち人間も自然の一部であり、一人一人遺伝子も異なる多様な存在だ。しかし、効率を追求するシステムは、多様性より画一性を好むため、そこに人間本来の姿との歪みが生まれてしまう。
利潤の最大化を追求するシステムでは、少しでもコストを下げるために同一の製品を大量に作ろうとする。そして、同一の製品が大量に売れるためには、多くの人に同一の価値観を持ってもらう必要があるから、マーケティングは自然と「画一的な豊かさ」の定義へと向かっていく。そして、大量に作った製品を買い続けてもらうためには、すぐに捨ててもらう必要があるから、計画的陳腐化が起こる。こうして効率の追求がもたらす大量生産・大量消費・大量廃棄システムが完成し、あらゆる問題を引き起こしているのが現代の経済と社会だ。
この歪みは、環境に対しては気候危機や汚染、生物多様性の喪失といった形で、社会に対しては人権侵害や差別といった形で負の外部性をもたらした。
昨今では、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)の発足に見られるように金融業や産業界においても「生物多様性」の重要性に対する認識がますます高まっており、一方では人権や差別といった文脈から「ダイバーシティ(多様性)」の重要性に対する認識も高まっているが、両者は決して無関係ではない。根っこにある問題は同じなのだ。

循環するシステムには、多様性が必要だ。自然界には廃棄物が存在しない。誰かの廃棄物は、必ず誰かの食料となる。それではなぜ人間の世界には廃棄物が出てしまうのか。それは、一つのものから多様な価値を引き出せる多様な価値観がないか、それらが出会っていないからだろう。廃棄物を価値ある資源とみなすためには、異なる価値観を持った人同士が出会う必要がある。同じ価値観を持つ人にとって、ごみは同じようにごみでしかないが、異なる価値観を持つ人は、そこに価値を見出せるのだ。
そう考えると、廃棄物のない世界に必要なのは、価値観の多様化であり、眼差しの多様化だ。人々の価値観が多様化し、異なる価値観に出会う機会が増えれば増えるほど、あらゆるものに価値が見出される可能性も増えていく。画一性を求めるシステムではなく、多様性を求めるシステムに変えていくと、価値は自然と見出され、結果として循環が生まれていくのだ。
画一性を求めるシステムの枠に自分を当てはめようとするのではなく、ありのままの自分を大事にすること。オセロのマスのように代替可能な □ になるのではなく、凸凹のままでいるからこそ、循環の鎖の輪をつなぐことができる。世界に多様性を増やすはじめの一歩は、自分らしくあることだ。
循環は「格差」を「差」にする。
上述した通り、循環するシステムには多様性が必要だ。多様性とはそれぞれが異なり、個体差があることを指す。循環にとって「差」とは歓迎すべき状態だ。
しかし、人々が持つこれらの差を、特定の価値観に基づいて特定の切り口から序列化すると、それは「格差」となり、社会問題として立ち現れる。「格上」「格下」という表現があるように、「格」という言葉には上下意識が包含されており、その裏には何を「上」と捉えるかという人々の眼差しがある。
たとえば、「経済格差」は「多くのお金を持っている」ほうが「格上」であり、より望ましい状態であるという社会的なコンセンサスがあってはじめて問題として成立する。
地球の資源の範囲内で社会的な公正の実現を目指す「ドーナツ経済学」を提唱するケイト・ラワース氏は、現在の経済をより「Regenerative and distributive(再生的で分配的な)」システムに移行する必要だと主張し、GDPの成長ではなく人々のウェルビーイングを重視すべきだと説明している。「分配」は、「再生」と並んで21世紀のキーワードとなる。
大量生産・消費・廃棄を伴う従来の直線経済は、経済的な豊かさという共通の物差しのもとで競争を促し、効率を追求し、富を生産してきた。競争の本質は「差」をつけることなのだから、経済競争を続ければ経済格差が生まれるのは当然だ。

しかし、よくよく考えれば自然界にも競争はある。むしろ自然界は生物同士の熾烈な競争の末に命が循環し、成り立っていることを考えると、「差」と同様に、競争すること自体は問題ではなさそうだ。問題なのは、競争のルールであり、物差しなのではないだろか。
社会的使命を持つ企業に与えられる「B Corp認証」は、「Best in the world(世界で一番)」ではなく「Best for the world(世界のために一番)」を目指すという理念を掲げているが、もし「世界のために」人々が競うなら、循環する経済と社会はあっという間に実現できそうだ。
「効率」や「生産性」の意味を再定義し、割り算の分母を「時間」から「資源」に変える。分子を「売上」や「利益」といった画一的な指標から、主観的で多様な「幸せ」という指標に変える。このように競争の物差しを変えていくことで、直線の経済が生み出した「格差」は、循環する経済に必要な「差」へと転換することはできないだろうか。
そのためには、人々の価値観の転換が必要だ。人々が「格」に対する自らの眼差しを変えていけば、システムの物差しも変わり、より分配的なシステムが形作られる。経済的な豊かさももちろん大事だが、それだけを「格上」に据えるのではなく、幸せのために人とのつながりや自然とのつながりも重視するようになれば、やがて「経済格差」もなめらかになっていくだろう。直線の眼差しを循環の眼差しに置き換えることは、あらゆる格差をなくす大きな可能性を秘めている。
循環する経済は、どこに向かうのか。
「サーキュラーエコノミー」という言葉の定義は、今もなお世界中で進化し続けている。
ユトレヒト大学のMartinCalisto Friant氏らは「A typology of circular economy discourses: Navigating the diverse visions of a contested paradigm」という論文の中で72に及ぶサーキュラーエコノミーに関わる概念を洗い出し、「経済に焦点を当てた断片的なアプローチか、社会全体に焦点を当てた全体的なアプローチか」「技術革新に対して楽観的か、懐疑的か」という2軸をもとにそれらの概念を「Reformist Circular Society(進歩型循環社会)」「Transformational Circular Society(移行型循環社会)」「Technocentric Circular Economy(技術中心型循環経済)」「Fortress Circular Economy(要塞型循環経済)」という4つのカテゴリに類型化している。

MartinCalisto FriantaWalter J.V.VermeulenaRobertaSalomoneb (2020) “A typology of circular economy discourses: Navigating the diverse visions of a contested paradigm” より引用
たとえば、「Reformist Circular Society」は、資本主義の修正により経済とサステナビリティを両立させ、技術革新により経済と環境のデカップリングは可能だとする考え方で、Cradle to Cradle、ブルーエコノミー、リジェネラティブ資本主義、ドーナツ経済学といった概念はすべてこの定義に当てはまる。
逆に「Transformational Circular Society」は、資本主義とサステナビリティの両立や技術革新によるデカップリングは不可能であり、システムそのものの移行が必要だとする考え方で、脱成長(Degrowth)や卒成長(Post Growth)、トランジション・デザインといった概念が当てはまる。
このように、循環をビジョンに掲げる経済や社会には様々な眼差しがあり、世界がどちらの方向に進んでいくのかはまだ分からない。一つだけ共通しているのは、いずれの方向も現状のシステムは持続可能ではなく、何らかの変化を必要としているという点だ。
循環とは、関係性のリ・デザイン
ここまで、ウェルビーイング特集の「脱炭素」「再生」「多様性」「格差」「あたらしい経済」という5つのテーマと「循環」という概念との関わりを探ってきたが、これらはすべて、私たちに眼差しの変革を迫るものだ。炭素と人間、自然と人間、人間と人間、経済と環境など、概念同士の関係性に対する眼差しを変えることが、循環するシステムを描くうえでの出発点となる。
循環の概念は、あらゆる境界線を曖昧にしていく。サーキュラーエコノミーは、消費者がリペアやリサイクルなどを通じて生産の一部に取り込まれるという点において、生産者と消費者との境目をなくしていく。循環するシステムに、廃棄物と資源の境目はない。
循環の視点で捉えると、人間は、料理を食べながら(消費しながら)、微生物のための料理をつくっている(生産している)とも言える。お皿を二つに割ればそれは破壊だが、見方を変えれば新たな二つのお皿を創造したとも考えられる。それを破壊とするか創造とするかは、人間が対象から機能を取り出せるかどうかという人間中心の考えに基づく分類であり、行為そのものに違いはない。循環の世界では、生産者は分解者であり、分解者は生産者でもあるのだ。

このように、循環というビジョンには、二つに分かれていたあらゆる概念の境界をなめらかにし、関係性をリ・デザインする力がある。
Cradle to Cradleの生みの親であるウィリアム・マクダナー氏は、日本で生まれ、幼少期に原爆の被災地である広島を訪れた際に衝撃を受けたこと、そしてその際に母親から日本の「間(ま)」という概念を教わったことが、現在の活動の原点になっていると語っている。
「なぜ人は殺し合うのか。」その問いから人と人との平和的な「関係性」の構築に興味を持ったマクダナー氏は、その後に国際関係を学び、建築の世界に入った。そして、建築を通じて人間と自然との関係性に目を向けるようになり、環境にマイナスの影響を与えない建築のあり方を模索する中で、1992年に「The Hannover Principles(ハノーバー原則)」を公表する。ハノーバー原則には、「人間と自然が共存する権利を主張する」「相互依存を認識する」「精神と物質の関係性を尊重する」といった原則が並ぶ。
日本で生まれたマクダナー氏が、人と人との平和的な関係性を問う中でその思想をやがて人と自然との関係性へと拡張し、Cradle to Cradleという考え方を生み出し、そしてそれがサーキュラーエコノミーという概念に進化していったことを考えると、循環する経済や社会の実現に求められるのは、私たちが無意識に線を引いて区別をしてきた概念同士の間に横たわる見えないつながりを捉える眼差しだという仮説はより確かなものに思えてくる。
循環という視点からあらゆる関係性を問い直し、人々の眼差しをリフレーミングすることで、循環する経済や社会という新たなビジョンは抽象的な概念から具体的なシステムに落とし込まれ、自然の循環の中に再びリカップリングされるのだ。
※本記事は、ハーチ株式会社が運営する「IDEAS FOR GOOD」からの転載記事です