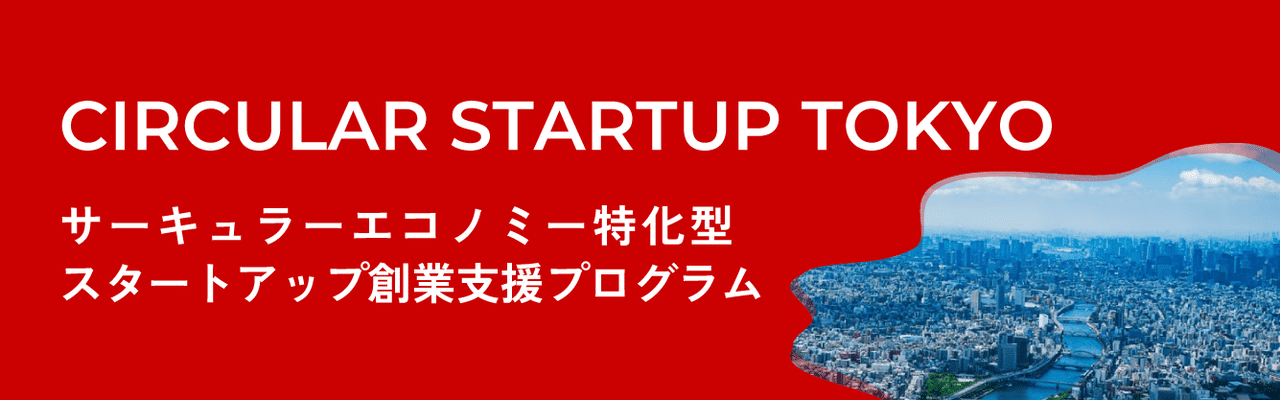2020年5月に経済産業省が約20年ぶりに「循環経済ビジョン2020」を公表し、同年10月には菅首相が2050年までの脱炭素社会実現を宣言、そして今年1月には経済産業省がかねてよりとりまとめを進めていた「サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス」を公表するなど、この1年で日本においてもサーキュラーエコノミー(以下、CE)に対する注目が急速に高まりつつある。
一方で、2015年12月に「サーキュラーエコノミーパッケージ」を採択し、5年以上にわたりCEを政策の柱に据えて移行を進めてきたEUでは、すでに移行に伴う具体的な課題も様々に指摘され、議論が進んでいる。今回は、それらの最新の議論にも触れつつ、実際に様々な企業のCE移行を支援させていただく中で実感する内容も踏まえたうえで、CEへの移行に向けて理解しておきたい課題について紹介したい。
サーキュラーエコノミーの実現に向けて理解しておきたい10の課題一覧
1. サーキュラリティ(循環性)は万能か?
CEをめぐる議論がWhat(CEとは何か)やWhy(なぜCEへの移行が必要なのか)から徐々にHow(どのようにCEへの移行を進めるか)へと移っていくにつれて重要性を増してくるのが、「サーキュラリティ(循環性)」の可視化だ。
CEを「概念」から「測定可能な指標」にすることは、真にCEへの移行を実現するうえで欠かせない。サーキュラリティを可視化し、客観的に比較可能なデータにすることで、具体的な数値に基づいてステークホルダーとコミュニケーションをとることができるようになり、CE事業・プロダクトはより投資家からも資金を集めやすくなる。また、サーキュラリティ可視化の過程で進められるDXは、さらなる事業効率の向上や顧客エンゲージメントの向上にもつながる。
世界では、英国エレン・マッカーサー財団が提供するCirculyticsや、WBCSDがオランダのスタートアップ、Circular IQと開発しているCTI(Circular Transition Indicator)、ルクセンブルク政府が主導して進めているPCDS(Product Circulality Data Sheet)など、すでに様々なサーキュラリティ測定ツールの開発が進んでいることは「サーキュラーエコノミー、2021年5つの注目テーマ」でもご紹介した通りだ。
一方で、「サーキュラリティ」という指標そのものが具体的に何を指すのかも含めて、この概念自体がまだまだ開発途上であることも理解しておく必要がある。オランダのCircle Economyは、2020年1月に公表した「The Circularity Gap Report 2020」の中で、世界のサーキュラリティは2年前の調査時の9.1%と比較して8.6%に下がっていると公表した。
同団体は、2017年に世界の経済システムに投入された資源の全体量は1006億トンで、そのうち920億トンが新たに採掘された資源で、残りの86億トン(8.6%)がリサイクルなども含めて利用後に循環し、新たに再投入された資源だと推定している。
しかし、Circle Economyは同レポートの中でこの「サーキュラリティ」の指標に関する課題についても触れている。
その代表例が、資源のInputからOutputまでにかかる時間軸の議論だ。経済システムがOutputした資源のうちどの程度が再びInputに戻っているかを示す「サーキュラリティ」という指標では、CEにおけるコアな原則である「製品寿命の延長」や「シェアリング」「再製造」など、一度Inputした資源をどれだけ長くシステムの中にとどめ、Outputされるまでの時間を伸ばすかという視点を反映できない。
また、サーキュラリティはあくまで資源の「量」にフォーカスした指標であり、その「質」を考慮に入れられていないという点や、あくまでサーキュラリティは「割合」を示すだけにとどまるため、経済システム全体が拡大した場合、仮にサーキュラリティが数値上は改善したとしても、バージン資源の投入絶対量が増えるという状況が起こりうるという点も指摘されている。
さらに、現在オランダ政府などは2050年までに100%CEの実現を目指しているが、そもそもサーキュラリティ100%は熱力学の法則から考えて実現不可能だという意見もあるほか、サーキュラーエコノミーはあくまで環境負荷と経済成長をデカップリング(分離)するための手段であり、サーキュラリティの向上自体を目的にすべきではないという意見もある。
これらの議論を理解するうえで参考になるのが、オランダの銀行大手INGグループが2020年1月に公表したレポート “Rethinking the road to the circular economy”だ。INGは、”Circular economy is a means, not an objective(サーキュラーエコノミーは手段であり、目的ではない)”と明言したうえで、経済がもたらす環境負荷を低減するうえで、CEはいつも最適なソリューションだとは限らないと説明している。例えば、農業セクターにおける気候変動への影響を削減するためには、畜産業における循環を考えるよりも植物由来食品への移行を進めたほうがより大きな効果が見込める、自動車業界でCEの原則を適用すると、現状すでに市場に投入されているガソリン車を「できる限り長く使い続ける」ことが重要になるが、温室効果ガス排出を削減するという目的のためには、ガソリン車をEV車に切り替えるほうがより効果的であるといった事例が紹介されている。
サーキュラリティを可視化し、継続的にモニタリングすることは重要だが、それがCEを推進するうえでの万能なツールではないということは理解しておく必要があるだろう。
一方で、エレン・マッカーサー財団のウェビナー「Circulytics 2.0: Improving measurement of circular economy performance」の中で実際に、Circulyticsを導入しているスウェーデンのアパレル大手H&MグループのUlrika Nordvall-Bardh氏は、その効果について、サーキュラリティの可視化に必要なデータを集めるプロセスや、それを通じて社内に生まれるコミュニケーションに価値があると話していた。
サーキュラリティの数値そのものだけではなく、サーキュラリティを可視化していくプロセスが自社のCE移行を進めていくうえで価値を持つという視点はとても重要だ。
2. サーキュラーウォッシングのリスク
CEがメインストリームになるにつれ、グリーン・ウォッシングやSDGsウォッシングと同様に、「サーキュラーウォッシング」とも言える事態が起こるリスクがある。筆者が2019年にオランダ・アムステルダムを訪問した際、先述したWBCSDのCTIを開発しているCircular IQのRoy氏は、アムステルダムではすでに何もかもがサーキュラーエコノミーだと宣伝され、混乱する状況が起こっていると懸念していた。
今後日本でもCEが盛り上がるにつれ、同様の事態が起こりうることは想像に難くない。だからこそCircular IQではサーキュラリティを可視化するソフトウェアの開発に取り組んでいるのだが、例えば「リサイクル可能な容器」と「コンポスト可能な容器」という選択肢があった場合、どちらが環境によいのかを消費者が正しく判断することは簡単ではない。
実際に、詳細な環境アセスメントを実施してみると、一般に想像されるのとは逆の選択肢のほうが実は環境にとって優しいということがしばしば起こりうる。例えばシンガポールのホテル大手マリーナベイサンズグループは、水の容器のLCA(ライフサイクルアセスメント)を実施した結果、紙やアルミニウムなどの代わりに使い捨てのプラスチックボトルを使い続けることを選択した。
国内においてもCEが盛り上がることはよいことだが、エレン・マッカーサー財団が同社の提唱する「バタフライ・ダイアグラム」においてループの優先順位を示しているように、サーキュラーエコノミーという広範な概念において何が優先されるべきモデルなのか、どちらの選択が環境負荷の観点からよりよい選択肢なのか、サーキュラー調達に関わる企業担当者やサーキュラー製品を購入する消費者は、より深い理解と多角的な検討が求められるようになるだろう。
3. PaaSとユーザビリティ
CEへの移行を実現するうえで鍵を握るビジネスモデルが、メーカーが製品の所有権を消費者に移行するのではなく、その所有権を保持したままユーザーに貸し出すという「PaaS(Product as a Serivce)」モデルだ。
リニア経済モデルの場合、メーカーは製品寿命を長寿化すればするほど新しい製品が売れなくなるため、環境負荷の削減と経済合理性との間にコンフリクトが存在していた。このジレンマを解消し、ロジックを180度逆転させるのがPaaSモデルだ。企業が製品の所有権を手放さないPaaSモデルにすれば、企業は製品寿命を伸ばせば伸ばすほど、資源生産性が高まり、一つの製品をより多く、より長く顧客に提供し、利益を出すことができるようになる。CEにおけるPaaSのポイントは、環境負荷の削減と経済合理性を一致させるという点にある。
米テラサイクルが展開する循環型ショッピングプラットフォーム「Loop」は、パッケージ(容器)においてこの仕組みを実現している。従来メーカーは使い捨て容器も含めて消費者に販売をしていたため、メーカーはいかにパッケージコストを下げるかという点に苦心していた。しかし、容器の所有権をメーカーが持ち続けることで、メーカーはより耐久性や機能性の高い容器の開発に投資を行うことができるようになり、結果として長期的な利益を生み出しやすくなるのだ。
一方で、PaaSモデルへの移行を検討するうえで課題となるのが、ユーザビリティの問題だ。ユーザーの視点からすると、最も利便性の高いPaaSは、必要なときに必要な分だけ利用し、不要になれば契約を解消して製品を返却できるという仕組みだと言える。しかし、PaaSにおいてユーザーの利便性を高めることが、CEの視点から必ずしも正解とは限らない。
例えば家具などのように輸送や回収を伴う製品をPaaSモデルにする場合、契約期間を短くして柔軟性を高めたり、「季節や需要に応じて家具を取り替えたい」などのニーズに応じて家具の交換をしやすくすることは輸送頻度の増加に直結し、そのぶん環境負荷が増えることになる。他にも、「家具が壊れた場合は無償で交換する」というサービスが、かえってユーザーの家具に対する取扱いの慎重さを損ない、結果として家具の破損を加速させる可能性もある。
また、オランダのINGグループでCEリードを務めるJoost van Dun氏は、PaaSモデルへのファイナンスを考えるうえでもジレンマがあると語っていた。PaaS事業に銀行が融資を行う場合、その際の担保は融資先のアセット(資産)ではなくどのぐらい利用者の契約を持っているかというコントラクト(契約)になる。そのため、銀行の視点からすると、より継続期間が長い契約のほうが担保としては価値を持つことになるが、その仕組みが契約者のニーズとコンフリクトを生むという意味だ。
CEへの移行に向けてPaaSモデルへの移行を検討する際は、どのようにユーザーの利便性と環境負荷、経済性のバランスをとるかという課題と向き合う必要があり、業界や製品カテゴリによってもそのベストプラクティスは異なってくる。そもそもPaaSが本当に最適な選択肢なのかも含め、慎重な検討を進める必要があるだろう。
4. 製品の所有権とデータの所有権
サーキュラリティの測定やPaaSモデルへの移行などCEに欠かせないのがDX(デジタル・トランスフォーメーション)だ。欧州ではすでに「マテリアル・パスポート」や「プロダクト・パスポート」という概念が生まれている。これらは、素材や製品に関する様々な情報をデータとして記録し、追跡することで、再利用や修理・リサイクルなどをしやすくするための取り組みだ。ICチップの埋め込みによる素材や製品のIoT化、改ざん防止のためのブロックチェーン上への記録など、テクノロジーを活用することで原料調達から回収にいたるまでのバリューチェーン全体で素材や製品の動きを透明化し、信頼性の高いデータを流通させることで真のCEを実現することを目指している。
しかし、ここで問題になるのが製品ユーザーのプライバシーだ。特にPaaSモデルの場合、ユーザーが製品をいつどこでどのように利用したかというデータは、製品回収後のリユースやリファービッシュ、リサイクルなどを進めるうえで非常に貴重な情報となる。製品の消耗度合いや回収時の品質を正確に把握できるようになれば、再資源化・再製品化に向けた効率も高められるうえ、リユースがしやすいように丁寧に製品を利用してくれたユーザーに対するインセンティブを提供するなどの仕組みも考えられる。また、ユーザーのニーズを細かく把握することは製品そのものの改善やカスタマイズにもつなげられ、廃棄の削減や顧客エンゲージメント向上にも活用できる。
一方で、製品利用時のデータはユーザーのプライバシーそのものでもある。豪・NZのメディア「The Conversation」は、2020年11月に”A circular economy could end waste – at the cost of our privacy(サーキュラーエコノミーは我々のプライバシーを犠牲にして廃棄物をなくすだろう)”と題する記事を公表しているが、まさにタイトルの通りである。
製品の所有権をメーカーが保持し、データの所有権もメーカーが保持するとなれば、メーカーとユーザーとのパワーバランスは崩れる可能性がある。CEにおいてメーカーがユーザーから回収しているのは製品だけではない。そこにはデータも含まれているのだ。そしてデジタルを基盤とするCE時代においてはそのデータにこそ大きな経済価値があることを考えると、誰がデータの所有者となるのかという点は今後より議論を深めていくテーマだと言える。
5. CEに競争優位性はあるのか?
CEへの移行を実現するうえで大きな課題となるのが「コスト」の問題だ。長期的な視点で見るとCEがリニア経済よりも経済的に競争優位であることは筆者も含めて多くの人が信じるところだが、短期的な視点で見てみると現実は必ずしもそうとは限らない。
例えば製品が故障したとき、修理するよりも新品を買ったほうが安ければ、消費者は新品の購入に流れてしまう。リサイクル関連企業を取材するたびに、リサイクル率が上がらないのは技術ではなく経済性の問題だという回答が返ってくる。CEへの移行を進めるためには、バージン素材よりもリサイクル素材の調達のほうが経済的に合理的な選択である必要があるし、リサイクル率を高めるためにはそもそものリサイクル素材に対する需要が必要となる。
このような状態を実現するためには、リサイクル素材の使用比率に関する法規制やバージン素材への課税など、経済外部性を内部化するための仕組みが必要となる。CEが競争力を持つような市場のルール作りは欠かせないだろう。
一方で、日本の経済産業省は「循環経済ビジョン2020」の中で、CEへの移行に向けて「規制的手法は最小限に、ソフトローを活用」すると明記している。その背景には、すでにCEを推進している日本企業はグローバルな市場で事業を展開しており、EUの規制も含めたグローバルな基準に沿ってCEへの転換を進めているため、日本国内における規制よりも、そうした企業の自主的な取り組みをCE移行への推進力にしたいという背景がある。
市場のルールも重要だが、それだけではなくメーカー同士が自主的に協働してリサイクル素材に対する需要を創り出す、CEのコストを下げるテクノロジーへのR&Dを推進するなど、CEを機会と捉えて「コスト」を「投資」に変えていく姿勢が求められていると言える。
6. リバウンド効果
CEを推進することで資源の利用がさらに加速するといった、予期せぬ効果をもたらすという懸念もある。INGも、先述したレポートの中でCEがリニア経済の製品を代替するのではなく、新たな市場の創出につながると、結果として資源の利用はさらに加速する可能性がある(例えば中古の修理済スマートフォンは、新製品の市場を代替するのはなく、それまでスマートフォンを手にすることがなかった低収入の人々に販売されている)、中古素材への需要が高まると結果としてバージン素材の価格が低下し、逆にバージン素材への需要を高める可能性がある、といったリスクに触れている。
エネルギー効率を高めることで、結果として人々の節約意識が薄まりエネルギーの無駄づかいが増えてしまい、エネルギー消費の削減量が相殺されてしまうという現象は「リバウンド効果」と言われているが、このような事態はCEにおいても十分に起きうることだろう。
例えば、CEのビジネスモデルの一つ、「シェアリングエコノミー」の代表例でもあるAirbnbなどの民泊プラットフォームは、人々がお互いに自分の空き部屋を貸し借りすることで、膨大な資源を投入して新たに宿泊施設を建設することなく、より多くの人が旅先で宿を確保できるようになる、非常にエコな仕組みだと言える。一方で、民泊物件数の増加により宿泊施設の供給量が増加すると宿泊費用は安くなり、結果としてより多くの人が旅行をするようになるため、移動による環境負荷が増えてしまうというリバウンドが起こる可能性もある。
このように、CEを推進することで本当に環境負荷は削減されているのかを多角的な視点から検討することは非常に重要だ。
7. “Design from Waste” と “Design out Waste”
エレン・マッカーサー財団が提唱するサーキュラーエコノミー3原則のうち、最も重要だと言われるのが「Design out waste and pollution(廃棄や汚染が出ない設計)」だ。CEとリサイクリングエコノミーの一番の違いはここにある。リサイクリングエコノミーにおいては、廃棄物をどのように有効活用するかという視点が重要となるが、CEは、そもそも製品設計の段階から廃棄物や汚染が出ないデザインをすることを目指しているのだ。
もちろん、いきなり廃棄物をゼロにすることができない以上、すでに排出されている廃棄物を有効活用し、アップサイクルやリサイクルを進めることは非常に価値がある。しかし、それはあくまでCEの側面の一つであり、最も優先して考えるべきはより前段階の製品設計であり、この廃棄物や汚染を排除する設計は「サーキュラーデザイン」と呼ばれる。
オランダのSustainable Amsterdamを運営するCornelia氏は、クールなアップサイクル製品が増えてきていることを歓迎する一方で、廃棄物は資源に変えられるという発想は、”Normalizing Waste(廃棄の常態化)”につながると懸念していた。
「Design from Waste」は、廃棄物に新たな価値を見出す非常にクリエイティブな取り組みであり、人々に廃棄物に対する新しい考え方をもたらすという点で非常に価値がある。実際に、Cornelia氏が懸念するように「資源になるなら捨ててもよい」と考える人もいれば、「資源になるなら捨てたくない」と考える人もいるだろう。リサイクルやアップサイクルが必ずしも廃棄の常態化につながるとは限らない。
一方で、最もCEを体現できるのは、「Design out Waste」であることは間違いない。最近は 「Right to Repair(修理する権利)」という考え方も広まってきているが、修理や解体、リサイクルがしやすい製品設計など、どのようにすればサーキュラーデザインが実現できるのか。そこにこそクリエイティビティを発揮する余地があり、イノベーションの機会がある。
8. サーキュラーデザインのジレンマ
上述したように、CEへの移行を実現するうえで鍵を握るのが「サーキュラーデザイン」だ。一方で、サーキュラーデザインの原則の中にも、様々なコンフリクトが生じうるということは理解しておく必要がある。
その代表例の一つが、「耐久性」と「リサイカビリティ(リサイクルのしやすさ)」のジレンマだ。2019年4月にGeorgia Institute of Technologyが公表した論文”Durability vs. recyclability: Dueling goals in making electronics more sustainable”は、この問題に焦点を当てている。
例えば、太陽光パネルのケースでは、薄膜パネルは液晶パネルと比較してリサイクルの費用対効果が高いものの、耐久性という意味では液晶パネルのほうが優れているという事例を挙げている。
他にも、製品の破損を防いだり耐久性を高めるために複合素材を接着するケースなどは、このジレンマが最も発生しやすいと言えるだろう。単一素材で製造する場合と比較して耐久性は高まるものの、耐久性向上のために異素材同士の接着強度を高めれば高めるほど、リサイクル時の解体コストは高まってしまう。サーキュラーデザインは、このように耐久性とリサイカビリティをどのように両立するかといったテーマに答えを出していく難しい作業でもある。
9. インクルーシブなサーキュラーエコノミー
サーキュラーエコノミーへの移行をいかに包摂的な形で進めるか、という点も大きなポイントになる。オランダのCircle Economyは2020年にCircular Jobs Initiativeを立ち上げ、CE移行に向けた「スキル育成」「仕事の質」「インクルーシブな雇用機会」の3つをテーマに掲げている。
再生可能エネルギーへの移行が進めば、化石燃料セクターで働く人々の雇用をどのように移行するかが重要となるし、新興国ではCEへの移行が廃棄物処理などに関わるインフォーマルセクターの人々の雇用に影響をもたらすというリスクも懸念されている。CEが新たな雇用を創出することは間違いないが、一方で経済システムの変革により失われる雇用もあるということを前提に、「Planet(環境)」「Profit(経済)」だけではなくどのように「People(人々)」の視点も踏まえながらCEへの移行を進めていくか、という点がこれからますます重要になるだろう。特に新型コロナウイルス感染症の拡大により貧困や格差の拡大が懸念されている今、CEに「People」の視点を取り入れる意義は大きい。
コロナ禍の真っ只中となる2020年5月、オランダのアムステルダム市が同市のサーキュラーエコノミー政策として「ドーナツ経済学」を採用した背景にも、CEに「People」の視点を取り入れたいという意図があった。地球の資源の範囲内で社会的な公正を実現し、誰もが繁栄できる経済・社会システムをつくるというドーナツ経済学の考え方は、環境・経済だけではなく社会の視点が含まれているためだ。
同年5月、時を同じくしてユトレヒト大学では「Online Utrecht Degrowth Symposium: From circular economy to circular society(脱成長シンポジウム:循環経済から循環社会へ)」と題するセミナーが開催されていたが、同イベントの趣旨も同様だ。背景には、CEを経済と環境のデカップリングという視点だけではなく、よりフェアで誰もに恩恵が行き渡る仕組みとして考え直す必要があるという問題意識がある。
日本では、神奈川県横浜市が「サーキュラーエコノミーPlus」というビジョンを掲げており、”Plus”に「人」の視点を重視するという意味を込めている。例えば、ヨコハマSDGsデザインセンターが運営する「ウッドストロープロジェクト」では、横浜市の水源である山梨県道志村の間伐材を利用した木製ストローづくりが行われているが、そのストロー製作には障がい者の方々が携わっている。ウッドストローの普及を通じて脱プラスチックを推進するとともに間伐材ニーズを喚起することで森林を再生し、かつ障がい者の方々にも雇用を生み出すという優れたドーナツ型のモデルだと言えるだろう。
CEの原則の一つでもある「Regenerate Natural Systems(自然のシステムを再生する)」の実践を通じて、自然だけではなくコミュニティも再生していく。これがポストコロナにおいて求められるCEモデルだと言える。
10.サーキュラーエコノミーと「成長」
最後のテーマは、サーキュラーエコノミーと「成長」だ。欧州においても「Green Growth(グリーン成長) vs Degrowth(脱成長)」の議論は盛り上がっており、2019年にアムステルダムを取材したときも同様の議論を耳にした。
この議論を考えるうえで、EUの欧州環境庁が2021年1月11日に公表した”Growth without economic growth(経済成長なき成長)”と題する記事が参考になる。EEAは、気候危機や生物多様性の喪失、汚染などは経済活動・経済成長と強く結びついているとしたうえで、経済成長と資源消費の完全なるデカップリングは実現不可能であるという可能性に触れており、今後の経済のあり方を考えるうえでドーナツ経済や卒成長(Post-growth)、脱成長(Degrowth)といった概念は、価値のある洞察を提供してくれると説明している。
EEAは、欧州グリーンディールは技術革新だけではなく消費や社会慣行の変化も必要としており、すでに文化や政治に深く染みついている「成長」という概念を改めて見直す必要性があると指摘している。また、EEAも記事の中で「100 % circularity is impossible(100%サーキュラリティは不可能)」だと明言している点も興味深い。
CEへの移行は長期的な競争優位や経済成長につながるというナラティブは、企業にとっては非常に魅力的だ。実際に、すでに資産運用大手のブラックロックが設定し、1年弱で9億米ドルの資金を集めたサーキュラーエコノミーファンドの銘柄にも組み入れられているフィリップスやNIKEといった企業などは、CEへの転換が事業成長につながることを証明してくれている(参考記事:「ブラックロック、サーキュラーエコノミーに焦点を当てた投資ファンドの募集、9億ドルに達する」)。
一方で、昨年にドーナツ経済モデルを推進するグローバルなネットワーク「Doughnut Economics Action Lab」がローンチし、アムステルダムをはじめとしてポートランドやコペンハーゲン、ブリュッセルなど世界中の都市でドーナツモデルが広がっていることや、先進的にCEに取り組んできたスコットランドやフィンランドなどがWEALL(Wellbeing Economy Alliance)に加盟し、GDPではなくウェルビーイングを豊かさの指標として「ウェルビーイングエコノミー」を推進している流れなどを見ると、Green Growth(グリーン成長)とは異なるナラティブが生まれつつあることも実感する。
フランスのESCP Business Schoolは2020年9月、“Between Green Growth and Degrowth: navigating the Circular Economy dilemma in a business school(グリーン成長と脱成長の間:ビジネススクールにおけるサーキュラーエコノミーのジレンマをナビゲートする)”と題するオピニオンを掲載しており、CEの概念はグリーン成長の支持者と脱成長の支持者を分断する傾向があるとしたうえで、同スクールでは問題の複雑さや企業・政府・テクノロジーの役割を理解するために、双方のアプローチを踏まえて多角的な視点から第三の道を模索していくとしている。
また、この議論を深めるうえでは英国のシンクタンクNew Economics FoundationのBeth Stratford氏が2020年12月に投稿している記事”Green growth vs degrowth: are we missing the point?”も参考になる。
個人的に最も示唆に富んだメッセージだと感じるのは、ドーナツ経済学の生みの親であるKate Raworth氏が2015年にオックスファムに寄稿したdegrowthに関する記事 “Why Degrowth has out-grown its own name.”の中で記している下記のフレーズだ。
“We have an economy that needs to grow, whether or not it makes us thrive. We need an economy that makes us thrive, whether or not it grows.”(「私たちの経済は成長を必要としている。それが私たちを繁栄させるかどうかに関わらず。私たちが必要とする経済は、私たちを繁栄させてくれる経済だ。それが成長するかどうかに関わらず。」)
また、ドーナツ経済学が目指すのは地球の資源の範囲内で社会的公正を実現することであり、その意味では二元論を脱却しているとも言える。先進諸国のようにドーナツの外側にいる(社会的公正は実現できているが、環境負荷もオーバーシュートしている)国家や都市にとっては脱成長が必要かもしれないし、ドーナツの内側にいる(環境負荷は地球の資源の範囲内だが、社会的公正は実現できていない)国家や都市にとっては引き続き経済成長が正解かもしれない。大事なのはそれぞれが現在地からドーナツの二重の輪の間に収まっていくためのベクトルを描くことであり、出発点によって進むべき方向は違うのだ。
CEの行き着く先はどのような経済であり、社会なのだろうか?この正解のない問いに対して自分なりの考えを深めていくことは、自身が「成長」に対してどのような立場をとるにせよ、より持続可能なシステムへの移行を進めていく上で価値ある時間となるはずだ。
【関連記事】Circular Economy Hub「サーキュラーエコノミー、2021年5つの注目テーマ」
【関連記事】サーキュラーエコノミー戦略により世界の温室効果ガス排出量約4割削減。Circle Economy最新レポート
【参照記事】Circle Economy “The Circularity Gap Report 2020”
【参照記事】ING Group “Rethinking the road to the circular economy”
【参照記事】”Circulytics 2.0: Improving measurement of circular economy performance”
【参照記事】Marina Bay Sands just chose single-use plastic bottles to serve water in Singapore—but it is not alone
【参照記事】【欧州CE特集#4】オランダ最大手ING銀行に聞く、サーキュラーエコノミーは金融をどう変えるか?
【参照記事】The Conversation ”A circular economy could end waste – at the cost of our privacy”
【参照記事】【欧州CE特集#10】アップサイクルのジレンマとは?「Sustainable Amsterdam」に聞くサーキュラーエコノミーの最前線
【参照記事】経済産業省「循環経済ビジョン」
【参照記事】Georgia Institute of Technology ”Durability vs. recyclability: Dueling goals in making electronics more sustainable”
【参照記事】【欧州CE特集#15】ドーナツ経済学でつくるサーキュラーシティ。アムステルダム「Circle Economy」前編
【参照記事】【特別対談・前編】横浜の「サーキュラーエコノミーplus」が描く、持続可能な都市の未来
【参照記事】Utrecht University ”Online Utrecht Degrowth Symposium: From circular economy to circular society”
【参照記事】EEA ”Growth without economic growth”
【参照記事】ブラックロック、サーキュラーエコノミーに焦点を当てた投資ファンドの募集、9億ドルに達する
【参照記事】ESCP Business School ”Between Green Growth and Degrowth: navigating the Circular Economy dilemma in a business school”
【参照記事】Open democracy “Green growth vs degrowth: are we missing the point?”
【参照記事】Oxfam “Why Degrowth has out-grown its own name.”